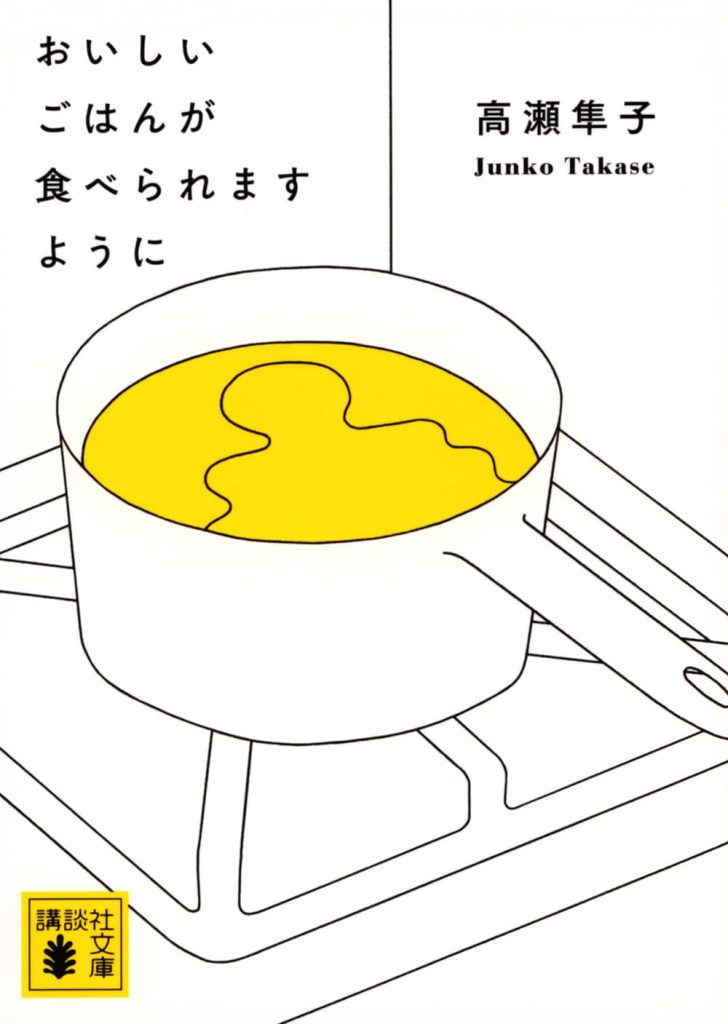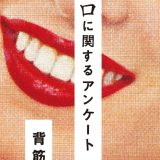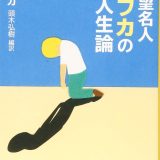職場のいざこざ、うんざりコロモー……

コロモーが落ち込んでいるのは珍しいですね。

何かあったんですか……?

実は、夕方ごろにゴミ出しをする当番なんだけど、

ゴミを出し終えた後で大量のゴミが発生して、二度手間になったんだよね……

(しょうもな……)

そのような些細なすれ違いからでも、会社の人間関係って簡単に崩れてしまうから大変ですよね。

そうなんだよー!!!

わざとじゃないって分かってはいるんだけど、

ゴミを出し終えた後で捨てに来る人もいて、心労極まりないよ~!

人それぞれが持つ常識があるように、コロモーはコロモーなりのポリシーを持っているようですね。

この内に秘めたるポリシー、どう大事にすれば良いの!?

そんな一冊「おいしいごはんが食べられますように」を今日は紹介します!

う、うおおおおお!!!?

あまりに現実的すぎる会社の人間関係のドロドロ。

必見です!
芦川は会社のみんなから守られる癒しキャラ。お菓子を作って会社に差し入れる度、色んな人から感謝される。一方の二谷は生きるために食べる、生きること以外の食事が億劫な彼は、芦川の差入れも例外ではなかった。ある日、芦川が苦手な押尾の「いじわるしませんか?と提案される。食を通じて、人間関係に小さな歪を生む芥川賞受賞作。

まず、この本を無理やりジャンルの枠組みにはめ込むとすれば、

強いて言うなら私は「サイコホラー」だと思います。

ふむふむ🍤

でも、この書籍の怖い点は「THE・サイコパス」みたいな怖さじゃなくて、

職場での嫌なドロドロを限りなくリアルに再現した、日常に潜む認識のズレから来る怖さがあります。

どういうこと……?

実際に経験したことはないけど、今後起こり得る可能性は十分にある。

そんな会社に対する、人間関係への根源的な恐怖がある書籍と思っています。

何と言っても細部までこだわりを感じる内容なんです。

確かに、ただ「お化けが出る」って言われるよりも、

「夕方に森の奥の秘密基地に行ってはいけない」とか「帰宅途中で後ろを振り返ると……」みたいな……

ディティールが深堀されていると“怖さ”って一気に増すよね😱

そうそう、そんな感じの怖さがあるんです!(笑)

この書籍には恋愛やミステリーに分類されるような要素もあります。

エビフライはそうした根源的恐怖も含めて、やっぱりサイコホラーなのかな?って思います。

この書籍のタイトルにもある通り、“食”が1つのテーマになっています。

「おいしいごはんが食べられますように」ってタイトルだしね!

主人公はおいしいごはんを食べられていないってこと?

話しの本質はそこにあるんです!

主人公が「美味しい」と発する場面はすべて、建前の言葉でしかありません。

主人公が一人で思いを馳せて食事をするとき、どんなに美味しそうなモノを食べても……

決して美味しそうには描かれないんです。

主人公も「生きるために食べる」みたいなことを言っていたよね!

そうなんです!

「生きるために食事する」と「食事を楽しむ」の2つに分断されるなら、

おそらく「生きるために食事する」派は少数派でしょう。

コロモーもできるなら楽しんで食事したいよ~!

社会は基本的に多数派の方が強いですよね。

だから「食事を楽しむ」のが普通で、「生きるために食事する」人は気を使わなければいけない。

でも、それって本当に平等なんでしょうか……?

むむむ……!?

平等って難しいコロモー……

それも会社という大きな枠組みで見てしまえば、食事への気持ちなんて小さな問題にすぎません。

本題はここからですよ!

物語としてはあらすじの通り、

仕事ができないけど会社から守られる存在の芦川さんへ意地悪をするお話しです。

仕事ができないのに、会社から守られる……

改めてそれだけ聞くと、会社として矛盾しているように思うけど、

それが正解のときもあるのが社会だから難しいよ~!

そうなんですよね……!

エビフライ的には、この部分が一番面白いポイントだと思ってます。

さっきの話しから引用すると、芦川さんは「食事を楽しむ派」の人を喜ばせるために努力を欠かしません。

一方でお仕事の方は疎か……

「生きるために食事する」人にとっては、ただ仕事のできない人って写るカモ……?

そう! そこのすれ違いが徐々に社内へ不和を生んでいくんです。

平等を望む人にとっては、お菓子の差し入れなんて作らず、しっかり人並みに仕事をしてほしいものです。

「意地悪」は平等を望むからこそ生まれた提案なのかな。

それもあると思いますね。

どの登場人物にも明確に悪!という点がないのが、妙にリアリティを感じる要因とも思います。

美味しそうに語られる場面こそないものの、

一人や二人、はたまた大人数で食事をする場面っていうのはいっぱい出てくるよね。

食事を「生きるため」や「意地悪の種」として語られたこの書籍。

そうですね。

“食”がテーマなのに肝心の味は語られず、目的や使命で食事する……!

今までの常識が根底から間違っていた気分コロモーだ……😢

確かに、これほど”食”を前面に押し出していて、

かつ、味の感想が出てこないのも珍しいですよね。

あまりにも浅い意見ですが、さすが芥川賞受賞作!ってところでしょうか。

でも、実際そうだよ!

「食事をする」って行為を社内の人間関係のドロドロと紐づけて、

根本から「食事をする」目的について考えさせられる。

これからコロモーはどんな気持ちでご飯を食べればいいんだ……

何もそこまで重く捉えなくても……😯

もう一つ思うことがあって、

「主人公がそうだから」って理由で、自然と芦川さんが悪者になっているけど、

読者の私たちも含めて、多くは芦川さん側じゃないですか?

言われてみれば……?

現実でこういう会社にいたら、

芦川さんの差し入れってすごく嬉しいし、主人公らの行動って過度に意地悪く見えるかもしれません。

確かにそうかも……!?

これって、さっきの「食事の捉え方」にも近い考えだね!

多数派・少数派、という括りで見ればそうですね。

ここでは芦川さんをプラスに捉えてる多数派と、マイナスに見てる少数派。

主人公たちはもちろん、少数派ですね?

むむむ……?

もし現実なら芦川さん派、だけど主人公たちの意見もしっくりくるから主人公たちが正しい。

むむむ……!?

つまり、自分と相いれない意見でも飲んでしまいそうになる「主人公補正」があると思うんです。

確かに、脳死で主人公たちを肯定して、芦川さんが悪と決めつけていたけど、

現実でいたとして、客観的に見て悪なのは主人公側……?

でも、芦川さんは仕事ができないし、

でもでも、仕事ができないだけで、意地悪をして良い理由にもならないし……

コロモーはもう、良く分かりません……

多分、正解はないと思います。

見る視点・個人の裁量によって、どちらが悪と思うかは変わってくるからね。

なるほど……!?

その曖昧さをこの書籍では、「食事」と「人間関係」に着目して、ドロドロに煮込んだ感じです。

どう頑張っても美味しくなさそう……

それを味わい尽くせるのは読書家だけでしょうね(笑)
この記事のまとめ
- “食”がテーマのサイコホラー!?
- 食事をする目的とは
- 美味しくなさそうな「ご飯本」
- ドロドロに煮込んだ不和
- 脆い職場の人間関係

「おいしいごはんが食べられますように」の読後直送、新鮮な感想をお届けしました。

結末まで読んでもハッピーエンドかバッドエンドか良く分からなかったコロモーだ!

これもまた多種多様な考え方ができる終わりカモね~……!

芥川賞受賞の話題作、ぜひ読んでみてください!